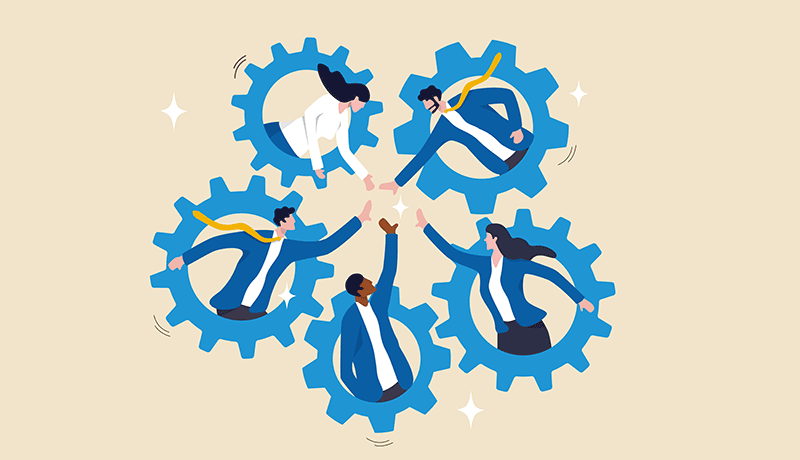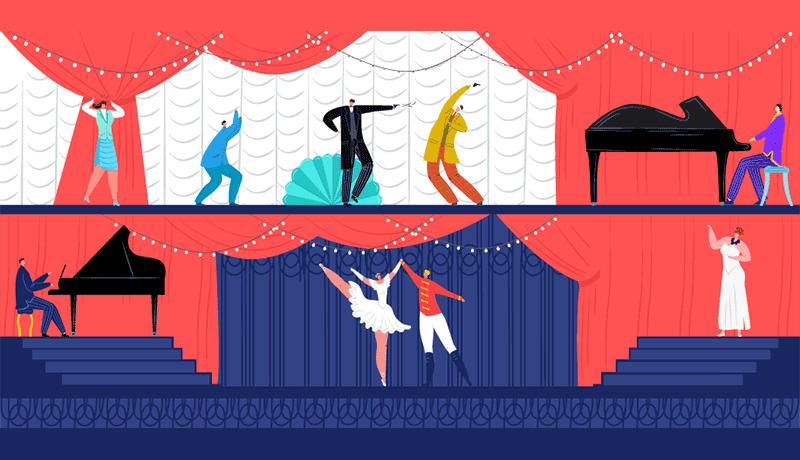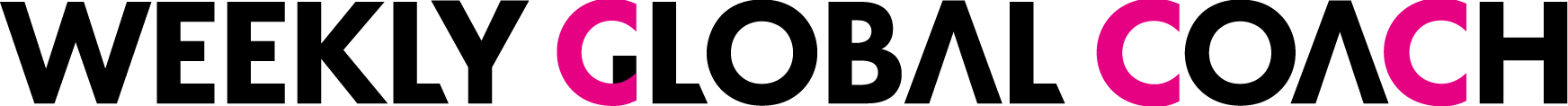Coach's VIEW は、コーチ・エィのエグゼクティブコーチによるビジネスコラムです。最新のコーチング情報やコーチングに関するリサーチ結果、海外文献や書籍等の紹介を通じて、組織開発やリーダー開発など、グローバルビジネスを加速するヒントを提供しています。
後継者に渡せないもの ~人はなぜ、役割を手放せないのか

「今こそ、私が最も役に立てるときなんです。まだ私を排除しないでほしい」
こう口にしたのは、某企業の元社長であるAさん。社長在任中には業績をV字回復させた功績もあり、社長職を退いてもなお会社に大きな影響力を持ち、重要な局面では彼の一言が空気を決める。そんな存在だった彼が、後継者へと経営が徐々に移っていくなかで発したこの言葉を聞いて、私は少し考え込みました。
なぜ人は、これほどまでに「役割」を手放せないのだろうか、と。
エグゼクティブコーチとして、幾度となく立ち会ってきた経営者の「引き際」。そこで繰り返し目にしたのは、経営のバトンを後継者になかなか渡せない姿、ときに渡したバトンをまた取り戻してしまうといった後退です。
それは権力への執着ゆえと思っていましたが、もしかしたらもっと根深い、誰もが持ちうる感情ゆえなのではないか…。
そう考え始めて、ふと2024年に放送されたNHK大河ドラマ『光る君へ』のワンシーンを思い出しました。
千年変わらぬ「退けない理由」
平安中期の貴族社会を舞台に、「源氏物語」を執筆した紫式部の生涯を描いた『光る君へ』に私はかなりハマりました。恋愛劇としての要素もありながら、権力・政治・社会変化の中で、人や組織がどう意思決定し、影響力を持つかを描いている点がほんとうに面白かったのです。
その中で、政(まつりごと)の頂きに君臨する藤原道長が、家臣の藤原公任らから引退を迫られる場面があります。自分自身はこれまで散々、ときの帝(三条天皇)に譲位を迫ってきたにも関わらず、道長は抵抗します。道長には道長の筋があるのです。
「摂政と左大臣、二つの剣を持ち、帝(みかど)をお支えすることが皆のためでもあると思っているが、それは違うのか」
道長は無能になったわけではありません。むしろ、自分がいることで朝廷が、政がうまくまわっているという確かな手応えがある。だからこそ「退く理由」が見つからないのです。
しかし、家臣の公任は冷静に時代の流れと政の安定を説き、「内裏の平安を思うなら、左大臣をやめろ」と迫ります。そして、道長はただただ言葉を失うのです。
テレビを観ながら思いました。これだけ耳の痛いことを進言してくれる部下や社外取締役、あるいはコーチを持っている経営者がどれくらい日本にいるだろう、と。同時に、人がなぜ後進に役割を譲れないのか、そのヒントを得た気がしました。
たしかに、「地位」や「権限」を失う怖さもあるでしょう。
ただそれ以上に、本当に尽力してきたトップほど手放し難いのは、「自分が役に立っている感覚」「こんなにも必要とされているという実感」ではないかと思うのです。
長年、組織の中心で決断し、自分の一言で物事が動き、感謝され、頼られてきた。そして、成果もあげ続けてきた。この体験は、自らの存在意義そのものになっていきます。
Aさんそして道長の引き際に触れ、「役割を譲る」とは、単にポストを渡すことではなく、自分の存在意義そのものを揺るがす行為なのだと私は思うようになりました。
「引き際」が難しい本当の理由は、ここにあるのではないでしょうか。
経営のバトンの渡し方−日米の違い
今、私は海外事業を担当しており、海外の企業に関わる機会が増えています。その中で、日本に比べ、アメリカでは経営のバトンが比較的スムーズに渡されていることを実感しています。
先月の米国出張で出会った米国人経営者たちも、後継に対して日本とは少し違うとらえ方をしていました。
彼らは言います。
「自分がいなくなっても会社がうまく回る。それこそがCEOとして最高の成果だ」
彼らの中では、「自分が役に立っているか」よりも「自分がいなくなった後も機能するか」が評価軸になっているのです。
アメリカでは、経営者は「任期付きのプロフェッショナル」なので、後継とは、役割と責任の交代であり、ゆえに権限も完全に移ります。一方、日本では、「経営者」とは単なる役職というよりは、「この人が居るからまとまる」という存在です。重要人物同士の関係のハブであり、企業の歴史や文化の体現者でもあります。よって、後継は、そうしたより広い機能や関係性の継承を意味します。だから前任者の影響力も残りやすいのです。
この違いは、個々の経営者の資質というよりは、文化や価値観、企業観や制度が積み重なった結果とも言えるので、単純には比較できませんし、どちらが正しいということでもありません。ただ、日本において、引き際が遅れたために思わぬ結果になったという経済ニュースが残念ながら少なくないことを考えれば、何らかの新たな視点は必要だと思うのです。
後継者に渡すべきものとは
ある元経営者とのコーチングセッションで、社長を退き会長となり、それを引退してもなお会議に呼ばれ続けていたその方は、こう語りました。
「自分が口を出さない方がいいと、頭では分かっているんです。でも、間違った判断をされるのを見るのは、正直、耐えられない」
その言葉は、とても人間的でした。
同時に、後継者が全責任を負って「間違う経験」をすることができないという事実も示していました。それは、後継者が役割のすべてを引き受ける機会を奪っているとも言えます。
後継者に本当に渡すべきものは、肩書きでも、権限でもありません。
それは、判断の重さを一人で引き受ける経験であり、覚悟なのだと思います。
誰かが背後に控えている限り、その重さは完全には渡らないのです。
経営者としての、最後で最も深い仕事
「今も一番、役に立てる」
Aさんや道長のこの言葉は、決して嘘ではないと思います。多くの場合、本当です。しかし、経営において問われるのは、「今、役に立っているか」ではなく、「自分がいなくなった後、何が残るか」です。
道長も、もし自分が去った後の政を想像できていたなら、公任の進言を違う形で受け取れたかもしれません。
後継者に最後の最後まで渡せないものがあるとすれば、それは地位でも権力でもなく、「自分が必要とされているという感覚」です。それを手放し、断ち切ることは、想像以上に勇気が要ります。
だからこそ、その勇気こそが、経営者としての最後の、そして最も深い仕事なのではないか、と私は思うのです。
《関連資料》
この記事を周りの方へシェアしませんか?
※営利、非営利、イントラネットを問わず、本記事を許可なく複製、転用、販売など二次利用することを禁じます。転載、その他の利用のご希望がある場合は、編集部までお問い合わせください。